住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
オーナーさま専用サイト
-
注文住宅
-
分譲住宅・
マンション -
賃貸住宅経営
-
土地活用
-
リフォーム
-
中古住宅売買
-
企業情報
住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
オーナーさま専用サイト
お役立ちコラム

【目次】

賃貸経営で得た家賃収入は、不動産所得として課税の対象になります。その際、サラリーマンとしての給与所得など、家賃収入以外にも所得がある場合は、すべての所得を合算した総所得金額をもとに税額を算出し、納税することになります。
個人に対する所得税の税率は、所得が多くなればなるほどに増える、「累進課税制度」を採用しています。この所得税に加えて、個人で納める税金に「個人住民税」もあり、個人住民税は課税所得に対して一律10%です。所得税と個人住民税をあわせた税率は、15~55%程度といわれています。
一方、賃貸経営を法人化した場合、資本金1億円以下の法人に対する実効税率は30%前後になります。「実効税率」とは、法人税など会社に対して課税されるいくつかの税金の税率から算出する税率です。
個人の税率は個人住民税をあわせて15~55%程度、法人の場合の実効税率は30%前後。つまり、個人の税率が実効税率を上回ったタイミングが、法人化への分岐点と考えられます。その分岐点となるのは、累進課税制度による個人の税率が、約40%以上(個人の所得金額が900万円以上1,800万円未満)になったら、法人化を考えてもいい時かもしれません。
給与所得を得ている方などは、現在の所得とアパート経営における収支計画を勘案し、個人経営、もしくは法人化を考えるとよいでしょう。また、アパート経営を始める前の段階で所得が900万円以上であれば、アパート経営開始と同時に法人化するのも一案です。
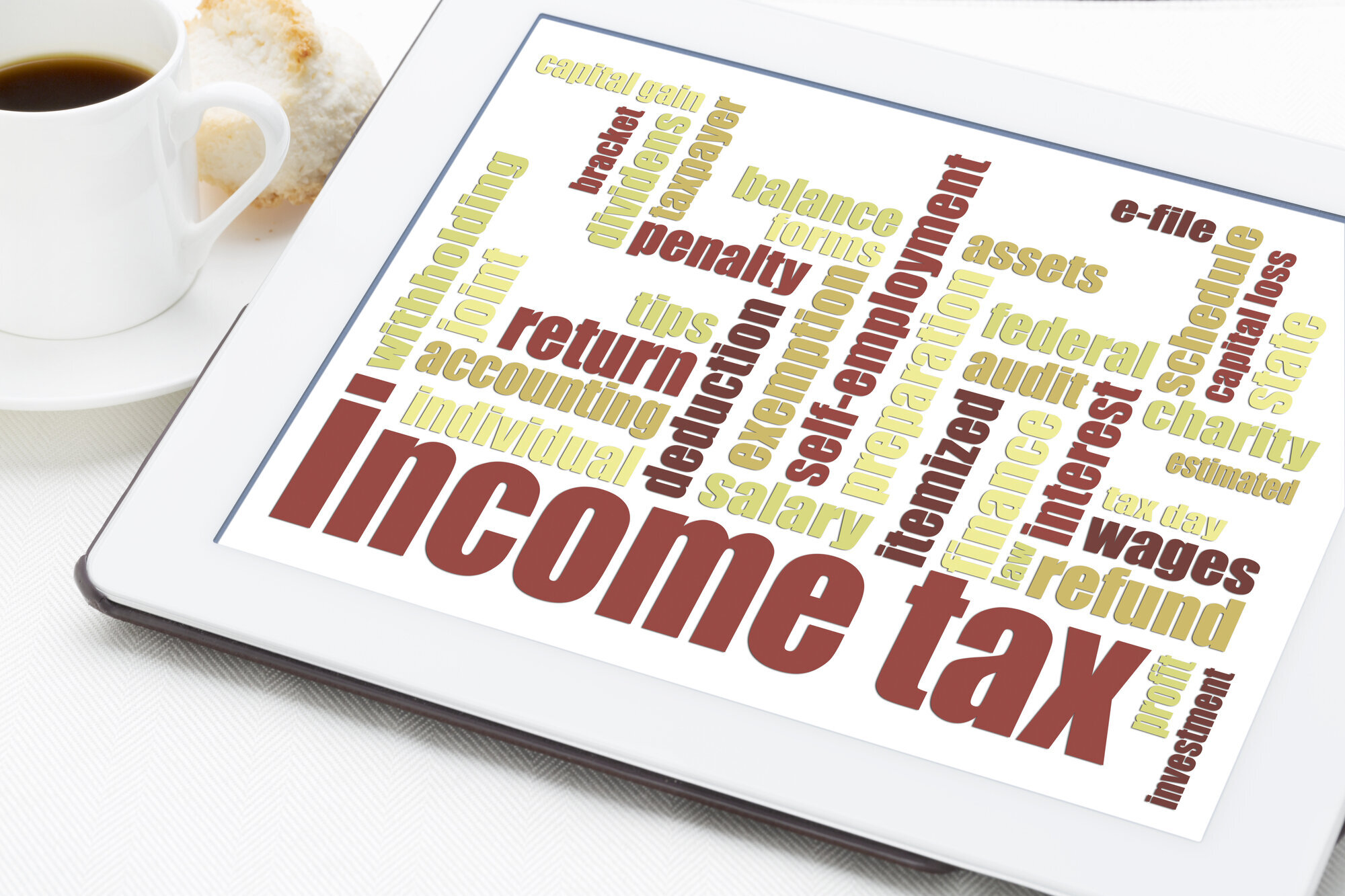
法人化の最大のメリットは、個人の所得税+住民税が実効税率を上回った場合、税金を抑えられるというところにあります。そのため、高額所得者ほど節税対策になると期待できます。
法人化するとオーナー様を役員とし、その役員報酬は経費として計上できるため、さらなる節税にもつながります。そして、家族を役員にして報酬を支払う、社員にして給与を支払うなど、所得を分散させることによって、所得税の税率を下げることも可能です。
個人、法人に関わらず、アパート経営を始めた直後は、初期費用を鑑みると帳簿上は赤字になることもあります。赤字の繰越期間は、青色申告を選択した個人事業主が3年、法人では10年です。これを「欠損金の繰越控除」と言い、欠損金(赤字)が発生した翌年度以降、繰越期間に利益が出た場合は利益と赤字を相殺できる制度です。法人は10年と期間が長い分、帳簿上の純利益を抑えられるため高い節税効果が期待できます。
株式会社にした場合は会社と個人が分離されるため、相続時にアパートなどの建築物なども“不動産”ではなく、“株式”に変わります。そのため相続対象を分割しやすく、トラブルを起こしにくいといったメリットも考えられます。また、賃貸経営を法人化して3年経過すると資産の評価額を下げることもできるため、相続対象となる株価なども下げることができます。
法人化するには費用が必要となるため、税金面でも負担はかかります。会社設立時の登録免許税、印紙税、建物を法人に譲渡する場合は不動産取得税などもかかります。
また、法人の場合はたとえ帳簿上が赤字であっても、均等割と呼ばれる法人住民税は納付しなければなりません。東京都の場合、資本金1,000万円以下・従業員50人以下の場合は7万円の法人住民税が課されます。
前述した欠損金の繰越制度はありますが、こちらは翌年以降に利益が出てはじめて使用できる制度ですので、利益が見込めにくい場合は、デメリットと捉えることもできます。

法人設立にあたっては、株式会社/合同会社の2つがもっともポピュラーでしょう。ただし、株式会社は決算公告の義務があるため、「官報」などに掲載する数万円の費用が毎年必ず発生します。
合同会社にその義務はなく、また株式会社のように役員任期による登録免許税もないため、経営の自由度が高いことが特徴です。司法書士など専門家への報酬費用を除き、株式会社は最低でも約21万円、合同会社は約6万円で設立することができますので、起業するにあたり、どのようにアパートを経営していきたいかを長期的に見据えて選ぶことが大切です。
税金面だけではなく、会社の維持にも費用がかかります。
法人化することで、社員が代表者1名のみであっても社会保険の加入が義務づけられています。社会保険料の負担は一般的に給与金額の約30%であり、会社と社員(役員)が折半します。
【まとめ】
ご紹介したように、個人の課税所得が900万円を超えた時が法人化を考えるひとつのタイミングと考えられます。また、アパート経営を始めるタイミングで法人化することが可能であれば、不動産取得税などの税負担を軽減することも可能となります。
法人化するメリットは所得税や相続税の節税、赤字の繰越などいくつかあげられますが、赤字でも法人住民税などの負担がある、設立時に費用が発生する、保険料の負担など細部まで考慮して検討することが重要です。
法人設立にあたって検討すべきことは多々あります。オーナー様のみで決めてしまうのではなく、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。