住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
オーナーさま専用サイト
-
注文住宅
-
分譲住宅・
マンション -
賃貸住宅経営
-
土地活用
-
リフォーム
-
中古住宅売買
-
企業情報
住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
オーナーさま専用サイト
お役立ちコラム

【目次】

まず、土地売却時にどのような税金が発生するのかをご紹介します。実際に土地を売却した場合に発生する税金は次の4つです。
その名の通り、収入から必要経費を差し引いた所得に課せられる税金で、税率は土地の保有期間で変わります。給与など土地売却の他に所得がある場合、土地の売却費用はその他の所得と合算せず、別に課税される分離課税。納めるタイミングは、売却した翌年の確定申告時になります。
それぞれの地方自治体に納める税金のことです。こちらも土地の保有期間で税率が変わります。確定申告をすると住民税の納付書が届くので、そのタイミングで納めます。
売買手続きに伴う契約書や領収書などにかかる税金です。土地の売却金額によって税額が変わります。契約成立時、契約書に収入印紙を貼る形で納めます。
法務局に土地の所有権などを登記する際、その手続きにかかる税金です。納めるタイミングは、土地売却の決済・引き渡し時となります。
売却した土地の所得税の課税対象となるのは、土地を売って得た金額ではありません。その金額から諸経費などを差し引いた金額(譲渡所得)から税額を計算します。そのため、まずは譲渡所得金額を算出する必要があります。計算式は次の通りです。
課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
「取得費」とは、土地を購入した時の価格、諸経費、登録免許税、印紙税などの合計です。もし土地の購入した時の金額や諸経費額が5%未満の場合、また取得費を調べることができない場合は、売却金額の5%相当額を取得費として計算することができます。
「譲渡費用」とは仲介手数料、測量費、解体費など。その他、条件が合えば後述する「特別控除額」を差し引くことができます。

次に納める税金を計算してみましょう。所得税、住民税に関しては、単純に譲渡所得金額に税率をかけて算出します。前述した通り、土地の保有期間によってその税率が変わってきますので、それぞれ具体的に見ていきましょう。
所得税は、毎年その年のすべての所得から所得控除を差し引いた金額に課せられる税金です。所得税はその性質によって10種類に分けられており、土地売却に関わる所得税はそのうちの「譲渡所得税」です。
税率は土地の保有期間によって変わります。売却した土地を5年以上保有していた場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、税率は次の通りです。
長期譲渡所得(保有期間が5年超) 15%
短期譲渡所得(保有期間が5年以下) 30%
併せて、確定申告の際に基準所得税額に復興特別所得税(2.1%:2037年まで)を申告・
納付する必要があります。
このように土地の売却に関しては、その土地の保有期間が大きく関わってきます。この保有期間は、土地を取得した日から売却した年の1月1日までの年数で計算されます。
例えば、2018年6月に購入した土地を2023年8月に売却したとします。実際の保有期間は5年2カ月ですが、計算上は売却した年の1月1日でカウントされるので、この場合の保有期間は4年7カ月という計算になります。
ただし、土地を相続した場合に限り、保有期間を被相続人から引き継ぐことができます。
所得税と同じく譲渡所得税であり、所得税と合わせて計算されるのが一般的です。こちらも土地の保有期間で税率が変わります。
土地の保有期間が5年超 5%
土地の保有期間が5年以下 9%
住民税は前年の所得に対して、1月1日時点で住民登録されている区市町村から徴収されます。注意したい点は納税の時期。所得税を確定申告で済ませた後、一般的にその年の6月頃から納付書が届きます。所得税を納めたタイミングで、住民税の納税も終わったと勘違いしないように注意しましょう。
また所得税、住民税はふるさと納税による控除が受けられますが「ワンストップ特例制度」は利用できないため、確定申告が必要になります。
印紙税は土地売買時に交わされる契約書、領収書などにかかる税金です。譲渡所得の金額に関係なく、納税額は契約金額(契約書に記載された金額)で変わります。
土地売買契約では契約書を2通作成するため、2通分の印紙が必要となりますが、一般的には売主、買主双方で1通ずつ負担します。
不動産に関わらず、船舶、航空機、会社、資格など幅広い分野にわたり、それぞれの登記や登録、認可や技能証明などを行う際に課税されるものです。土地の売買に限って言えば、土地を名義変更する際に発生します。土地の売買時に必要な登記は「所有権移転登記」と「抵当権抹消登記」の2つです。
所有権移転登記は、土地を引き渡す際に登記簿上の所有者を買主に変更します。この時に発生する税金は、買主が負担するのが一般的です。
土地を担保にローンを組んでいる場合、ローンを完済した時などに行うのが抵当権抹消登記です。まだローンが残っている状態で土地を売却する際にも必要となり、その手続きにも登録免許税がかかります。
金額は、不動産(土地、建物など)ひとつに対して1,000円。例えば土地と合わせて家屋も売却する場合は、土地ひとつ、建物ひとつと数えて、2,000円です。
また抵当権抹消登記は司法書士に依頼するのが一般的なので、司法書士への報酬も必要になると考えておきましょう。一般的に、相場は1~2万円前後と言われています。
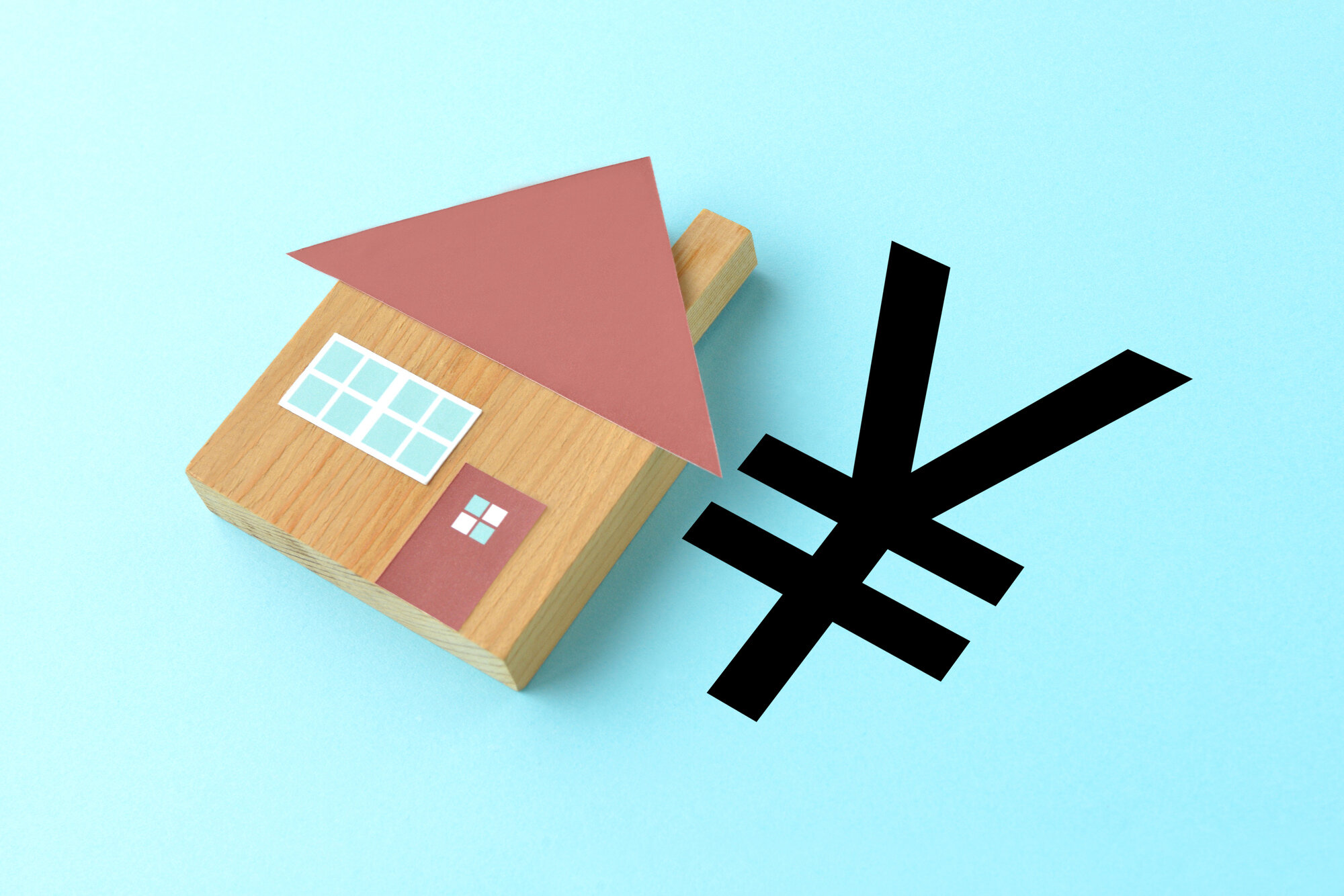
それではどのくらいの税金を納めることになるのか、実際にシミュレーションしてみましょう。
仮に1,500万円で購入した土地を30年間保有、2,000万円で売ったケースで計算してみましょう。計算が複雑にならないよう、諸経費などは想定額として設定し、登録免許税、印紙税、仲介手数料などは諸経費に含むものと仮定します。
購入金額 1,500万円
購入時の諸経費 120万円
売却金額 2,000万円
売却時の諸経費 100万円
譲渡費用 80万円
保有期間 30年
前述した計算式に当てはめて計算すると、譲渡所得は次のようになります。
2,000万円(収入金額)-(1,500万円+120万円+100万円+80万円(取得費+譲渡費用))=200万円(譲渡所得金額)
次に所得税、住民税を計算します。土地の保有期間が30年ですから、長期譲渡所得の税率が適応されます。所得税は15%、住民税は5%です。
所得税 300,000円
住民税 100,000円
長きにわたる相続などにより土地の取得費が不明な場合は、前述したように売却金額の5%を取得費として計算することになります。
最後に、土地売却で節税するために知っておきたい特別控除をご紹介します。
実際に自分が住んでいる土地を売却する場合、保有期間に関係なく最高3,000万円までの控除が受けられる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」があります。ただし、住んでいた家を取り壊した場合には1年以内に、またそこに住んでいない場合にはその日から3年経過する日の年の12月31日までに売却する必要があるなど、控除を受け継ぐための要件がいくつかあります。控除を受けた上、売却の収益が3,000万円以下の場合には、譲渡所得税はゼロになります。
さらに、その家の保有期間が10年を超えていた場合は軽減税率が適用されます。売却収益が6,000万円までは所得税10.21%、住民税4%となり、マイホーム売却の3,000万円の控除と併用も可能。ただしどちらも、納税額がゼロになった場合でも確定申告は必要です。
その他にも公共事業のために土地を売却した場合、相続した土地を規定年数以内に売却した場合などさまざまな特別控除がありますが、どれも売却先や期間など、細かい要件を満たす必要があります。
【まとめ】
このように土地の売却にかかる税金は特殊です。すぐに土地を手放すことはなくても、事前知識があるだけでいざという時にスムーズに事を運ぶことができるでしょう。
ただし、いざ土地を手放すことになった場合は、必ず税理士など専門家へ相談しましょう。この先税率が変更される可能性も高く、正しく処理するにはプロの知見が必須となります。
税理士へのつてがない場合も、ハウスメーカーなどに相談すれば、提携している税理士を紹介してくれることもありますので、土地売却の可能性が発生した場合は、時間に余裕をもって専門家に相談するようにしましょう。