住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
オーナーさま専用サイト
-
注文住宅
-
分譲住宅・
マンション -
賃貸住宅経営
-
土地活用
-
リフォーム
-
中古住宅売買
-
企業情報
住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
オーナーさま専用サイト
お役立ちコラム

【目次】
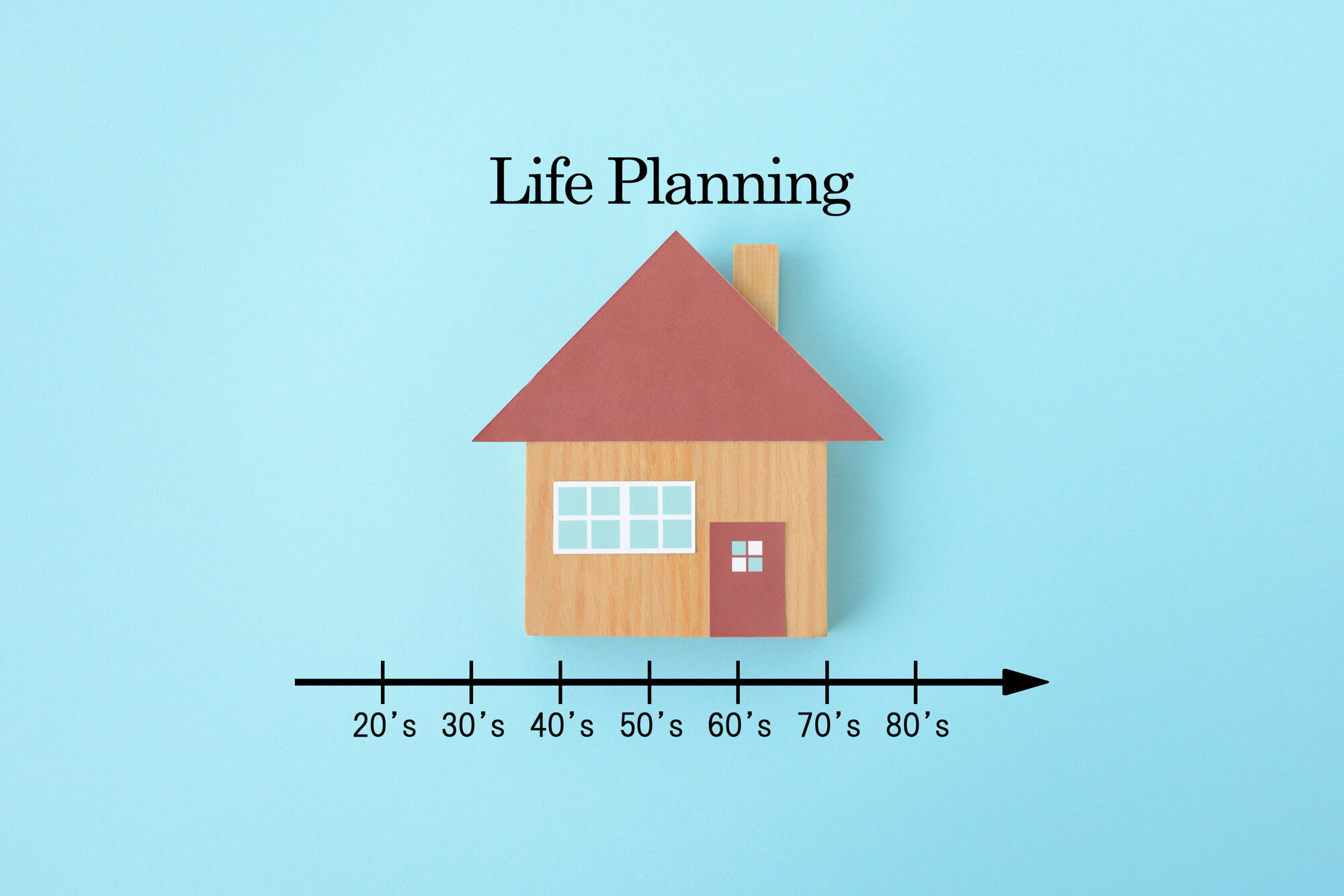
まずはアパート経営を始めるまでの流れを確認しておきましょう。まず、アパートを建築する土地があることは大前提です。事業計画を立て実際にアパート経営をスタートさせるには、大きく分けて「アパート建築」と「入居者募集」の2つのプロセスがあり、それぞれについて解説します。
①建築会社の情報を集め依頼先を決定する
アパートの建築を依頼する会社の情報を集め検討します。ハウスメーカーや建築会社といっても手がける建物の種類や規模はさまざま。賃貸住宅の実績がある会社を中心にリサーチするのが安心です。専門部門のある大手企業の中には、周辺の賃貸市場をリサーチし、資金計画を含めた事業計画の提案から行う会社もあります。また、建物を建築するだけでなく、アフターメンテナンスや定期点検など、長期的な目線で選ぶようにしましょう。
②アパートのプランニングを進める
ハウスメーカーや建築会社の担当者とともに建物の規模、間取り、外観などの詳細を決めていきます。アパートの規模や間取りは資金計画やターゲット(=想定する入居者)に密接にかかわるため、理想とする事業計画から外れていないか、十分に検討して進める必要があります。建物の大枠が固まったあとには内装材や設備機器などの細部の選定を行います。
③建築確認の申請を行い、承認されたら着工する
アパートが建築基準法やその他条例に則しているかどうかの審査を受けるため、自治体または民間の指定機関に申請書を提出します。
④アパートが完成したら完了検査の申請をする
アパートの完成後、完了検査の申請を行います。検査済証の交付を受けるとアパート建築が無事に完了したことになります。
以上がアパート建築の流れです。次に入居者募集の流れを確認しましょう。
①賃貸管理会社を選ぶ
賃貸管理業務をプロに任せる場合、できるだけ早めに契約する賃貸管理会社を選定します。実際に店舗を訪ねるなどして、アパートを建てる地域の特徴や賃貸需要について詳しく、信頼できそうなスタッフを抱えている会社を見極めることが大切です。
②入居者募集を開始する
入居者の募集はアパートの完成前から開始するのが一般的です。間取りなどが決まった段階で賃貸管理会社に詳細を伝え、募集を開始してもらいます。特に家賃についてはあとから増額することは難しいため、事業計画に沿って慎重に設定しましょう。
③入居審査を行う
入居希望者の応募があればアパートの内見を実施、入居を決めてくれた場合は入居申し込みの手続き後、オーナーさまと賃貸管理会社による入居審査を行います。入居審査とは、入居者と連帯保証人について家賃の支払い能力などの確認をすること。アパートがまだ建築中の場合は、仮押さえ(入居審査を先に行い、アパート完成後に内見してもらう)の形で受け付けます。
④賃貸借契約を結ぶ
物件の詳細や家賃、入居ルールなどを記載した賃貸借契約書を作成し、入居者の署名捺印と初期費用の支払いによって契約が完了します。

アパート経営を始めるまでの流れを確認したところで、収益が出る仕組みについて考えてみましょう。アパート経営でオーナーさまが受け取る収入は、毎月の家賃と賃貸借契約時に支払われる礼金です。ここから必要経費(修繕費、管理費、保険料、各種税金など)を差し引いた分が収益になります。
アパート経営の大きなメリットとして、収益を得られる仕組みが途切れにくいことがあげられます。「入居者募集→入居審査→賃貸借契約→物件管理→入居者退去」という流れを繰り返すことがアパート経営の流れになりますが、入居者に長く住んでもらうこと、退去通知を受け取ったらすみやかに次の入居者募集を開始することで、長く安定的な収益を期待できます。
入居者については、あらかじめ賃貸管理会社と希望する人物像(年齢層や勤務先など)を打ち合わせ、条件などを共有しておくことで、オーナーさまの理想とする入居者の募集から、長期の賃貸借契約が期待できます。また、新しい入居者の募集は、退去通知を受け取ったタイミングですぐに開始してもらいましょう。空室期間をできるだけ短くすることは、収益を途切れさせないことに必須です。

ここまでアパート経営で収益が得られる仕組みを確認しました。アパート経営で利益を出し続けるためには、空室がなく、すべての部屋が入居している状態の「満室経営」をめざすことが非常に大切です。
最後に、入居者が途切れないアパートにするために特に心がけたい点を3つご紹介します。
家賃が安いコンパクトなワンルーム物件を求めている人もいれば、家賃は多少高めでもゆったりとした1LDK物件を求めている人もいます。アパート経営を予定しているエリアで人気のある賃貸物件はどんな物件なのかを研究し、入居者ニーズに合ったアパートを建てることが「満室経営」につながる需要なポイント。「アパートのプランニングを進める」プロセスで、しっかり検討することが不可欠です。ハウスメーカーや建築会社から、周辺の賃貸市場のリサーチに基づいたコンサルティングを受けるという選択肢もあります。
アパート経営を行う際に気になるのはライバルの存在。同規模の近隣アパートにはない強み(=付加価値)を持たせることも、「満室経営」の有効な戦略になります。付加価値とは、駅から近い、眺望が良いなど、もともとの立地に左右されるものばかりではありません。大きめのキッチンがある、収納スペースが充実している、ペットが飼えるなど、入居者にとって魅力的なプランや条件を検討し、「選ばれる物件」を目指しましょう。
入居者が長期契約してくれれば、アパート経営の安泰につながります。長く住み続けてもらうためには、条件のいい物件、居心地のいい物件と入居者に感じてもらう必要があります。そのためにはオーナーさまも賃貸管理会社とともに、共用部分の管理や専有部分のメンテナンスなどに気を配ることが大切です。

近年の賃貸住宅市場では、単なる「住む場所」ではなく、「暮らしの質」を高められる物件が選ばれる傾向にあります。暮らしの質を高める方法について、特に「環境」と「暮らし」の2つのポイントから解説します。
省エネ性能の高い物件は、以下の3つの理由から今後ますます需要が高まることが予想されます。
・法律の改正
ひとつ目は、建築物省エネ法(正式名:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)の規制強化です。2025年4月からは、小規模の賃貸住宅も含め、新築建築物にはすべて、省エネ基準への適合が義務付けられます。
この法律に基づいて、住宅などの建築物に、事業者が表示するラベルが「省エネ性能ラベル」と呼ばれるものです。ラベルを活用することで、入居者が建物の省エネ性能が把握しやすくなるため、省エネ性能を求める入居希望者にアピールして入居を促進することができます。
参考:建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表⽰制度|国土交通省
入居希望者はラベルを参照することで、エネルギー消費性能や断熱性能、目安光熱費、ZEH水準およびネット・ゼロ・エネルギーなどが確認できます。
・環境問題への意識の高まり
SDGsへの関心が社会全体で高まるなか、環境に配慮した物件であることをアピールすることで、物件の資産価値を高めることができます。他の物件と比べた場合の差別化要素となるでしょう。
・光熱費の高騰
2022年以降のロシア・ウクライナ戦争や円安の影響の他、気候変動の影響などで、入居者の光熱費負担は年々増加しています。
高断熱・高気密の物件や太陽光発電システムを導入した物件は、光熱費削減につながるため、たとえ設備の導入によって家賃が割高になったとしても光熱費の削減分で納得してもらいやすくなります。
多様な入居者層のニーズに対応できる設計も、大きなポイントです。
一般に、入居者のなかでも、単身者とファミリー層では求める住環境が大きく異なります。
単身者は、コンパクトでありながら機能的な間取り、通勤の利便性、セキュリティの高さなどを重視する傾向があります。
一方、ファミリー層は、十分な収納スペース、子どもの遊び場や教育施設へのアクセス、騒音対策などを重視することが一般的です。
立地や住宅の条件などによっては、入居者を単身者/ファミリー層のどちらかに絞るのか、どちらの層も狙える物件を目指すかなど、戦略を練ることが重要になるといえるでしょう。
どちらの層も狙うのであれば、単身者向けの部屋とファミリー層向けの部屋を分けるなど、設計面での工夫が必要になるでしょう。例えば、同じ建物内に1Kタイプと2LDKタイプを混在させることで、多様なニーズに対応できます。
また、将来的な間取り変更が可能な可変性の高い設計を採用することも、長期的な視点では有効です。

新築賃貸住宅で他の物件との差別化を図るためには、戦略的なアプローチが必要です。競合物件との違いを明確にし、入居者に選ばれる物件を目指しましょう。
物件の設備などを具体的に考える前に、まずは周辺の競合物件をリサーチすることが重要です。周辺エリアの賃貸物件について、以下の点などを詳細にチェックしましょう。
1)家賃相場
・間取りタイプ別の平均家賃
・駅からの距離による家賃の変動
2)設備
・標準的に備わっている設備
・付加価値として提供されている設備
3)間取り
・人気のある間取りタイプ
・供給はが少ないが、需要がありそうな間取りタイプ
・敬遠されやすい設備(室外洗濯機置場、バランス釜給湯システムなど)
4)空室率
・物件タイプ別の空室状況
・空室が多い物件の特徴
競合する賃貸住宅にない魅力を、どんなポイントで作るか考えていきましょう。
物件全体をリフォームすることが難しい場合は、特定の部分や設備に費用をかける「一点豪華主義」戦略も検討してみましょう。コストを抑えながら差別化を図れる他、長期的な入居につながる可能性が高まります。
導入しやすい設備の代表的な例として挙げられるのが、無料・高速のインターネット回線です。単身・ファミリー層どちらの入居者からも人気が高く、近年、新築の賃貸物件では無料インターネットを設備として導入することが一般的になってきています。
また、スマートホーム技術を導入してみることも考えられます。スマートホームとは、照明や温度調整、セキュリティ設備などについて、自動化や遠隔操作する技術のこと。今後ますます普及が進むと予測されています。
この他、以下のような設備もぜひ検討してみてください。
・キッチン
ファミリー層や、家での時間を大切にする層にアピールできます。
特に人気が高いのが、備え付けの食器洗い乾燥機。家事の時短につながるとして、特にファミリー層向けの施策で活用されやすい設備です。
・バスルーム
日々の疲れを癒す空間として、多くの入居者が重視するポイントです。例えば、広めの浴槽や、最新のシャワー設備などを検討してみましょう。
他、浴室乾燥機能なども、梅雨時や冬場の洗濯物に対応できることから好印象をもつ人が多い設備です。
・収納
単身者・ファミリー層、どちらにも重視される収納スペース。
スペースを確保できそうであれば、シューズインクローゼットやウォークインクローゼットなど、広めの収納をぜひ検討してみてください。

アパート経営を進めるうえで重要なのは、経営にまつわるリスクをできるだけ事前に把握しておき、対策を講じることです。アパート経営で起こりがちなリスクや、その対応方法について解説します。
新築アパートの建築では、建築費、設備費用などの初期投資が高額になることが一般的です。
その中で更に経営状況が深刻になりやすいのが、空室率が想定よりも高くなり、家賃収入で初期投資を回収できないケースです。専門家と相談しながら、事前の対策を十分に練りましょう。
・資金計画の見直し
運営を開始する前に、満室の場合だけでなく、予想以上に空室が発生した場合の立て直し方なども考えておきましょう。
・補助金や助成金、その他公的制度の活用
特別償却、税額控除、研究開発税制などの制度を活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。自分で探すことはもちろんですが、専門家に相談することも忘れないようにしておきましょう。
また、省エネ対策や耐震性強化などに関する補助金は地方自治体によって異なります。プランニングを始める前に必ずチェックしておきましょう。
空室の発生はローン返済や運営費用に直接影響します。空室が長期化しないよう、先手を打った対策を講じることが重要です。
・ターゲット層を明確にする
アパート経営を始める前に、市場を分析することを必ず忘れないようにしておきましょう。年齢層や家賃相場、周辺の空室率、交通アクセスなど、地域特性を把握したうえで、需要のある物件を提供することが重要です。
・管理会社やプロに任せる
経営方針をご自身ひとりで決めることに不安がある場合は、管理会社やプロに運営を任せるのも一つの手段です。
管理会社に運営を委託すると、入居者募集や物件管理を任せることができます。
賃貸広告の作成・掲載、入居希望者の審査、賃貸契約の締結などを代行してもらえるため、経営方針の検討など、本来注力すべき業務に専念できます。
さらに運用の手間を軽減したい場合は、一括借り上げもひとつの手法です。これは、不動産会社などが賃貸住宅全体を一括で借り上げ、代行して運営するもの。
たとえば、パナソニック ホームズでも一括借り上げのサービスが提供されています。
住宅のプロによる建物・設備の管理やメンテナンスによって賃貸住宅の価値をより長期間持続させるなど、きめ細かなバックアップによってアパート経営をサポートします。
さらに空室の有無にかかわらず、毎月全室分の借り上げ賃料が支払われるため、収入の目安が立てやすいのが大きな特徴です。ただし、空室時の家賃は市場相場よりも低く設定されることが一般的なため、注意しましょう。
【まとめ】
アパート経営を始めるために必要なプロセスは、賃貸住宅の建築と入居者募集を計画的に進めること。魅力ある賃貸住宅を建てて、ていねいに入居者へのケアを行うことで「満室経営」が続けられれば、家賃収入も継続します。長く安定した収益を得られる仕組みが、アパート経営の大きな魅力と言えるでしょう。
 |  |  |