住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
オーナーさま専用サイト
-
注文住宅
-
分譲住宅・
マンション -
賃貸住宅経営
-
土地活用
-
リフォーム
-
中古住宅売買
-
企業情報
住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
オーナーさま専用サイト
お役立ちコラム

【目次】
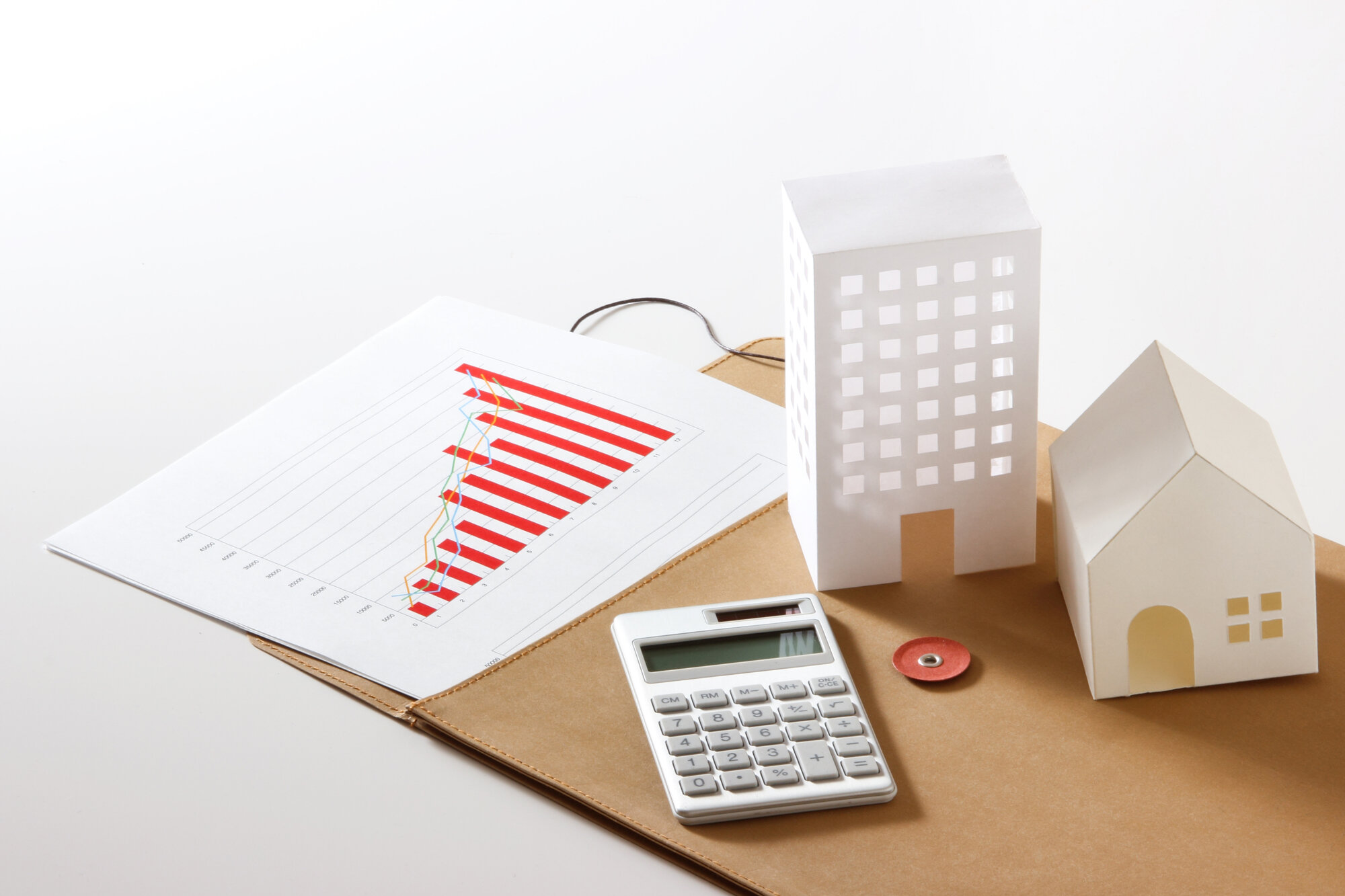
アパートやマンションなど賃貸経営を始める以上は、持続可能なビジネスとして成功させたいものです。そのためには、賃貸経営が社会に果たす役割を踏まえたうえで、必要な知識を習得し、しっかりと利益を出していくことが必要です。
賃貸経営というのは、住む場所を必要としている人に住居を提供して対価をいただくという、社会的にも重要な役割を担う事業といえます。このことから、なんらかの資格が必要なのでは?と思う方もいるかもしれませんが、実際には特別な資格は必要ありません。アパートやマンションを所有さえすれば、誰でも賃貸経営を始めることが可能です。
しかしいくつかの資格を取得することによって、必要な知識や倫理観を体系立てて身につけることができます。賃貸経営を進めていくと、不動産会社や銀行、建築施行会社、管理会社、借り手など、さまざまな相手方との間で、いろいろな判断をしなければいけない場面が多く出てきます。このとき、正しい知識を持っていれば、状況に応じた適切な判断をすることが可能になり、損をするなどのリスクを大きく減らすことができます。
知識があることは自信につながりますし、資格を持っていることで、交渉を有利に進められる場面もあるかもしれません。資格取得のための学習に時間がかかるのは事実ですが、長期的にはメリットが大きいため、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
賃貸経営を始める際には、以下のような知識を身につけておくとよいでしょう。
借地借家法は、賃貸人(貸す人)よりも、賃借人(借りる人)に有利な法律となっています。これは、賃借人のほうが一般的には弱い立場に置かれるケースが多いことから、対等な立場での自由な契約行為を原則とする民法よりも、賃借人をできるだけ保護するように制定されているためです。これらの法律の趣旨を正しく理解しておくことが肝要です。
賃貸経営において、収益を正しく把握し、将来にわたり適切な収支予測を行うためには、会計や税務に関する知識が必要です。建物や設備の減価償却など、賃貸経営に特徴的な会計の概念や、税金の仕組みについてしっかり押さえることで、理想的なキャッシュフローを目指しましょう。
賃貸住宅の運営では、賃料の決定と入居者の募集に始まり、入居審査、入居後のクレームやトラブル対応、設備管理、賃料の収納や滞納対応、更新対応や退去後のリフォームなど、多くの管理が必要です。これらは専門の管理会社に任せることが多いと思いますが、実務的な知識を持っておくことが、有事の際のスムーズな判断につながります。

「賃貸不動産経営管理士」は、賃貸住宅の管理に関する知識やスキル、倫理観を持った専門家に与えられる国家資格です。かつては、3つの公的な不動産関連業界がそれぞれ独自で資格の運営を行っていましたが、その社会的な重要性から資格の統一が図られ、2021年に国家資格の位置づけになりました。
資格取得用のテキストには、建物の管理に関する知識だけではなく、入居者募集や空室対策といった経営的観点や、賃貸借契約や相続などの法律的観点、税金対策、建物や設備自体に関する基礎知識など、幅広い領域をカバーしており、賃貸オーナーにとっても、さまざまな状況に対応できるよう学ぶ価値は大いにあります。
管理業務主任者は「賃貸住宅の業務を遂行する全般的な知識」にフォーカスした国家資格です。関連する法令や規約、管理組合の円滑な運営、長期修繕計画の策定など、管理に関わる全般的な知識を広く学びます。
「不動産実務検定」は、かつては「大家検定」と呼ばれていた、不動産運用にまつわる実践知識を体系的に網羅した民間の資格です。2級、1級、マスターの3種類の検定があり、不動産経営の基本について順を追って学ぶことができます。
例えば2級検定では、賃貸管理運営に関する知識として、空室対策、滞納トラブル、法律、基本的な税金対策をカバーします。前述の国家資格に比べると取得も比較的容易で、いつでも受験が可能なので、国家資格にこだわりがない方はこの資格から始めてみるのもよいでしょう。
「住宅診断士(ホームインスペクター)」とは、住宅の劣化状況や不具合事象の有無、改修必要な箇所や、改修が必要になる時期、改修にかかるおおよその費用などを、目視の範囲でチェックし、第三者的な立場でアドバイスを行うための民間の資格です。
賃貸経営の立場からも、所有する住宅の状態を自身で「一次診断」することで、改修のための予算を事前に想定しておくなど、経営計画の作成に役立てることができます。
「土地活用プランナー」は、その名の通り、土地の活用方法について、さまざまな観点から多角的な検討を行ったうえで、土地オーナーに対して適切な提案を行えるようにするための民間資格です。国家資格ではありませんが、内閣府から公益認定を受けた「公益社団法人 東京共同住宅協会」が認定しており、公益性は高いといえます。
この資格を持つことで、不動産業者からの土地活用提案が適切なものかを自身で判断できるようになりますから、理想とする収益化の可能性は高まるといえるでしょう。

ここまで、不動産に直接関連する5つの資格について解説してきました。次は、少し視点を変えて、経営やビジネス全般に関わる2つの資格を紹介します。資格取得へのハードルは上がりますが、賃貸経営をより広いビジネスの観点から俯瞰的に捉えることで、新たな可能性が広がるはずです。ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
「中小企業診断士」は、中小企業の経営課題への診断と助言を行う専門家(経営コンサルタント)を認定するための国家資格です。企業経営に関わる知識を横断的に身につけることができるため、「日本版MBA」と呼ばれることもある、ビジネスパーソンに最も人気の高い資格のひとつです。
賃貸経営も「経営」の一種ですから、経済学や経済政策、財務・会計、企業経営理論など、資格取得の過程で学んださまざまな知識を自身の賃貸経営に適用することで、「大家さん」から「経営者」に視座を上げることができるようになります。
「ファイナンシャルプランナー(FP)」は、「お金のホームドクター」とも呼ばれ、個々人の資産状況や収支状況、将来のライフプランなどを分析して、最適な資産設計・資金計画を提案、アドバイスを行う専門家です。ファイナンシャル・プランニング自体は職業の名前ですが、資格としては、CFP ®資格、AFP資格と呼ばれる民間資格のほか、FP技能士1級~3級という国家資格があり、FP技能士1級はCFP ®資格と、2級はAFP資格とほぼ同等水準とされています。なかでもCFP ®資格は、世界標準資格として国際的にも通用する資格ですので、海外との仕事が多い方はこちらを目標にするのも良いかもしれません。
FP資格を取得することで、資金計画、資産運用、税務、不動産、相続、事業継承といった金融知識を得ることができますので、賃貸経営を行ううえでも役立つはずです。
【まとめ】
賃貸経営は、特別な資格を持たなくても誰でも始めることができます。しかし、資格を取得するための勉強をすることで、さまざまな分野をまたいで立体的に知識を身につけることができ、成功の可能性は大きく高まります。紹介した資格に興味があるようでしたら、オーナー様ご自身で詳細を調べていただき、賃貸経営者としてのスキルアップに役立ててみてください。