住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
オーナーさま専用サイト
-
注文住宅
-
分譲住宅・
マンション -
賃貸住宅経営
-
土地活用
-
リフォーム
-
中古住宅売買
-
企業情報
住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
オーナーさま専用サイト
お役立ちコラム

【目次】

相続税の節税を考えるのであれば、相続財産としては現金や株式よりも土地・建物で遺した方が効果的です。その理由は、相続税を計算するための財産評価額が抑えられるからです。現金や株式は額面金額がそのまま評価額になりますが、土地は時価の80%程度とされる「路線価」で評価され、建物は固定資産税評価額で計算されます。
さらに、その土地に賃貸住宅が建っていれば、節税効果は飛躍的に上がります。貸家建付地は自用地よりも土地や建物の評価額が低くなるからです。賃貸住宅の建築時に住宅ローンを組んでいるのであれば、ローン残高は債務として財産から控除されます。
相続税の納税にはまとまった現金が必要になり、しかも納税期限は「相続の開始があったことを知った日から10か月以内」となっています。納税資金を捻出することが難しいのであれば、相続財産から相続を予定している人に賃貸住宅を生前贈与して、そこから得られる家賃収入を将来の納税資金にした方が節約になる場合もあります。
または、相続人が賃貸住宅を新築する資金を援助して、住宅取得等資金の特例措置が適用されれば非課税で贈与することができます。ただし省エネ等住宅の場合には1000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの限度額があります。
相続と贈与のどちらが得になるかはケースバイケースなので、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続税対策は、生前のうちから進めておくことが大切です。相続税は、優遇措置を最大限利用することで大幅に減額できる可能性がありますが、前提として納付期限内に相続税を払う必要があります。納付期限に間に合わないと優遇措置が使えなくなり、逆に延滞税が加算されることもあるので注意が必要です。
相続税の納付期限は、被相続人が亡くなってから10か月以内と定められています。しかし、何も準備をしていなければ、その期間は相続手続きをするために、被相続人の財産目録(預貯金や株式などの金融資産、不動産などを含む全財産)を作成し、法定相続人全員から意思確認を得ながら、必要書類を準備する必要があるため、決して長いとは言えません。生前に遺産を透明化して相続人の間で共有するか、被相続人の意思を反映した遺言書などを作成しておくと、相続税を計算する手間がかなり軽減できます。もちろん、財産や相続人の調査ができる司法書士や弁護士にあらかじめ相談しておくのもよいでしょう。
相続税対策を考える際、土地の値上がりや建物の評価額などの変動があるため、最適な方法は常に同じではなく、選択する方法によっては、最終的に節税になる場合やむしろ逆効果になる場合もあります。
相続税対策として土地に賃貸住宅を建てても、新築して間もない場合は評価額が高く、最終的に相続税の軽減にならない可能性があります。計画性をもって、家族で早めに相談しながら進めることで、効果的な節税対策となります。
生前贈与を有効活用すれば、財産の一部は孫など法廷相続人以外にも非課税で贈与できる場合があります。ただし、ほとんどは用途や対象、上限金額が明確に定められているので確認が必要です。具体的な用途としては、子や孫の結婚・子育て資金、 教育資金、住宅取得等資金などになります。なお、住宅取得等資金の特例措置は2026年末までとされているので、将来的に廃止される可能性があります。
用途を限定されない生前贈与としては、毎年1月1日から12月31日までの年間110万円までは非課税という基礎控除を活用した、「暦年贈与」と呼ばれる方法があります。ただし、暦年贈与によって被相続人が亡くなる前の7年以内に受けた贈与は相続財産とみなされてしまうことは覚えておきましょう。また、暦年贈与は記録を残しておかないと、税務署からあらぬ疑いをかけられる恐れもあります。現金手渡しは避けて、口座振り込みなどで資金の移動を証明できるようにしておくと安心です。
2015年の税制改正により、相続税の基礎控除額が大幅に減少しています。
(改正前)基礎控除額 =5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
(改正後)基礎控除額 =3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、7000万円の相続財産があって、法定相続人が3人いる場合を考えてみましょう。
改正前であれば、基礎控除額は5000万円+1000万円×3=8000万円なので相続税はかかりませんでしたが、改正後の基礎控除額は3000万円+600万円×3=4800万円となるため、
7000万円-4800万円=2200万円が課税対象となります。
相続財産と法定相続人の数を確認して、基礎控除額を超えそうな場合は、早い段階で対策を考えた方が良いでしょう。

相続税対策は、早めに手を打つほど効果的です。40~50代であれば、親世代が健在である場合も多く、被相続人として考えることもあるでしょう。家族全体の問題として、相談し合える環境を整えることも大切です。
60代に入ると、自身の終活を意識し始める人も増えてきます。子ども世代に自分の財産をどのように遺すかを検討し、意思を決定したなら、相続人が手続きしやすいように遺言書として書き残しておくことも思いやりになります。
財産を現金や株式だけで遺すのは、相続税対策としてはあまりおすすめできません。状況によってはマンション購入、アパート経営、資産管理会社の設立なども視野に入れた方が有効な対策になると言えるでしょう。これらは一朝一夕でできることではないので、長期的な視野で取り組むことをおすすめします。
【まとめ】
相続税の節税を考えるのであれば、非課税や減税の対象となる控除や特例は最大限に有効活用したいもの。なかでも生前贈与の基礎控除には使い道が限定されていないものもあり、かなり有効な手段となります。しかし、そういった控除や特例は、条件を満たさなければ使えません。
せっかくの機会を失ってしまわないように、控除・特例を使える条件は何か、現状では贈与と相続のどちらが有利なのか、税制の仕組みにアンテナを張っておくことが大切です。
税制改正は毎年行われるので、将来的に控除・特例の内容が変わる可能性は考えられます。こうした変化に柔軟に対応できるように、税金に関して相談できる税理士やファイナンシャルプランナーをはじめとする、アドバイザーをつくっておくと良いでしょう。
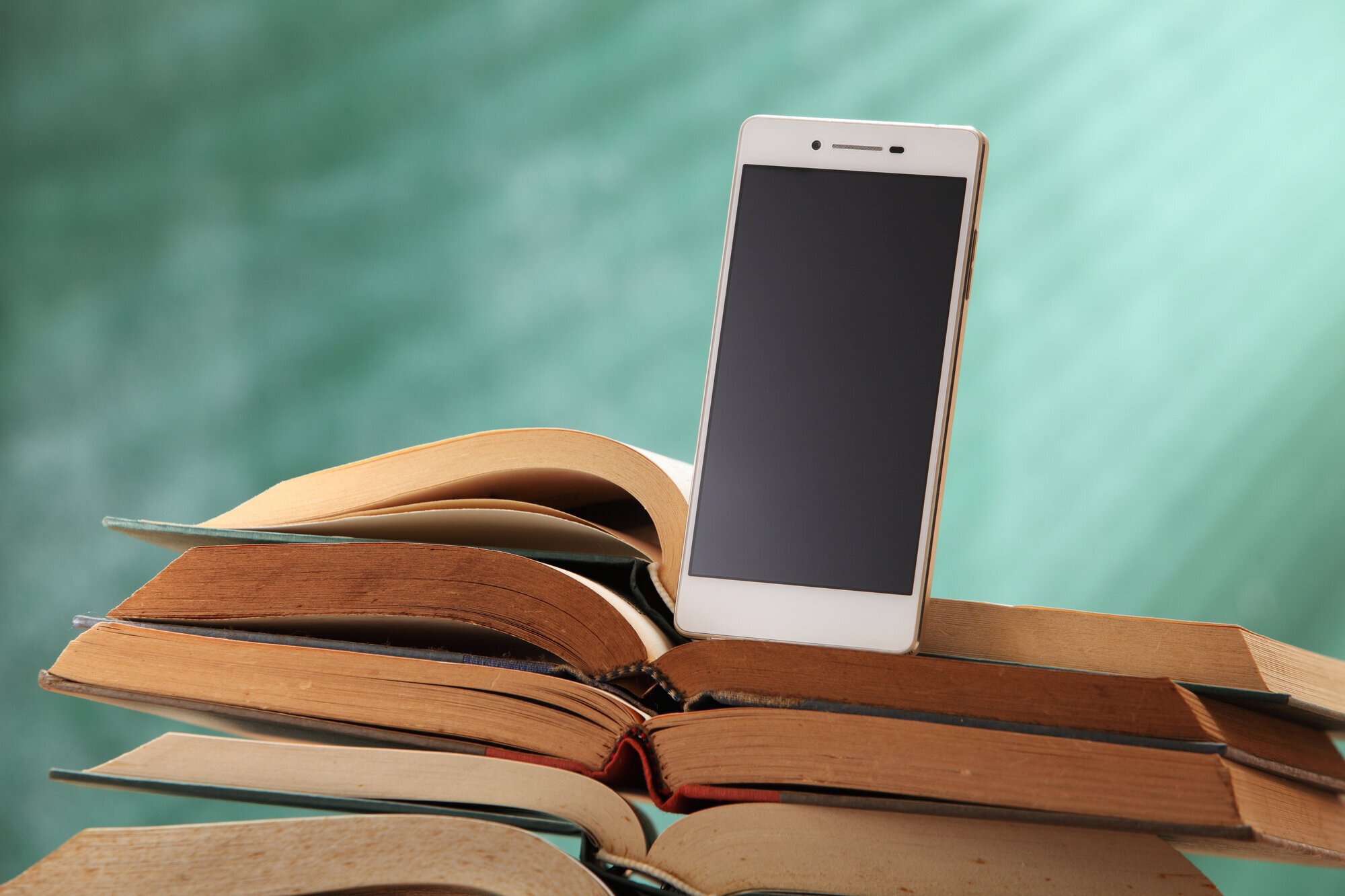 |  |  |