住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
オーナーさま専用サイト
-
注文住宅
-
分譲住宅・
マンション -
賃貸住宅経営
-
土地活用
-
リフォーム
-
中古住宅売買
-
企業情報
住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
オーナーさま専用サイト
お役立ちコラム

【目次】

賃貸住宅を含む建物全般には「法定耐用年数」が定められています。これは、建物は経年によって劣化していき資産価値が減っていくため、それに応じて減価償却費を決定するために定められています。
つまり、法定耐用年数とはあくまで資産としての価値を示すための税務上のもので、建物が使えるかどうかなどの物理的な状態とは必ずしも関係がありません。
法定耐用年数は建物の構造によって異なり、鉄骨造は軽量鉄骨造か重量鉄骨造かによって異なります。
<構造別の法定耐用年数>
税務上、土地については年数の経過とともに資産価値が減少することはありません。一方、建物については年数が経過すると資産価値が減少します。たとえば軽量鉄骨造の賃貸住宅の場合、法定耐用年数は27年のため、27年を超えると税務上は資産価値がゼロになります。
法定耐用年数は資産価値の「目安」としての年数です。それに対して耐久年数は、建築会社が独自の調査・試験などを行い発表している、建物や設備が問題なく使用できる期限のこと。法定耐用年数と比較して、建物の物理的な寿命に近いものだといえます。
ただし周囲の環境によって、またメンテナンスを怠っていると必ずしも耐久年数通りに建物の状態が保たれるとは限りません。

法定耐用年数は、建物の資産価値に密接に関係するため、建物への課税額を左右する要素になります。それではそもそも減価償却費とはどのようなもので、法定耐用年数によって建物への課税額はどのように変動するのでしょうか。
税制上の固定資産(資産としての土地や建物の総称)のうち、土地とは異なり、建物は経年劣化することで、建築した際から価値が少しずつ下がっていきます。その価値を会計上にも反映させるために、「減価償却」というルールが定められています。
また、オーナーさまが賃貸住宅経営のために建物を建築した場合、建築費の一部は経費として計上されます。しかし、建築費の一部を建築時に一括して経費として計上することは、その後もオーナーさまが事業のために建物を継続的に使用している、という現実からは乖離した会計処理になってしまいます。そういった要素もあり、オーナーさまは建築時から少しずつ下がっていく「減価償却費」を毎年経費として計上することができます。
賃貸住宅経営において、法定耐用年数と減価償却費が関わってくる場面として、確定申告のタイミングがあります。確定申告をもとに課税される所得税は、オーナーさまの家賃収入から経費を差し引いた不動産所得に対して課税されるため、経費として減価償却費を計上していくことは節税対策につながります。減価償却費は「取得価額×償却率*」で計算され、取得金額(建築費)が5000万円である重量鉄骨造の賃貸住宅の場合、法定耐用年数は34年で、償却率は0.03となり、減価償却費は5000万円×0.03=150万円となります。つまり、34年間にわたり毎年経費として150万円を計上できるということです。
ここで気をつけたいのは、建物の構造による法定耐用年数の違いです。
例えば重量鉄骨造の建物であれば、木造の建物とは12年間の差がある、約1.5倍の期間減価償却費を経費として計上することができます。先ほどの例に当てはめれば、150万円×12年なので1800万円の差となります。そのため、建物を建築して賃貸住宅経営を始める際は、建物の構造によって異なる減価償却費の計上期間も計算に入れて計画を立てることが重要です。
また、注意しておきたいのは、減価償却費を計上できるのは法定耐用年数の期間内という点。重量鉄骨造の場合34年間を超過すると減価償却が完了し、それ以降は減価償却費を経費として計上することはできなくなってしまいます。
*償却率…国税庁「減価償却資産の償却率表」にて公表
法定耐用年数は不動産相続の場面でも使われます。相続時に建物の価値は築年数と法定耐用年数を比較することで算出されます。木造の法定耐用年数は22年、重量鉄骨造は34年のため、相続した建物の築年数が25年以上であれば、木造ならば資産価値はゼロとなり、重量鉄骨造ならば資産価値は4分の1以下になっているということになります。
逆に築年数の浅い建物の場合、建物の資産価値が残っているため、課税額が大きくなります。相続する可能性がある場合には、事前に生前贈与などで計画的に継承を進めておくとよいでしょう。
相続の場合は、法定耐用年数が経過している建物のほうが相続税の課税額を抑えることができるため、相続を前提として賃貸住宅を建築する際は、より法定耐用年数が短い木造の建物を建築した方が相続時には有利になるといえます。
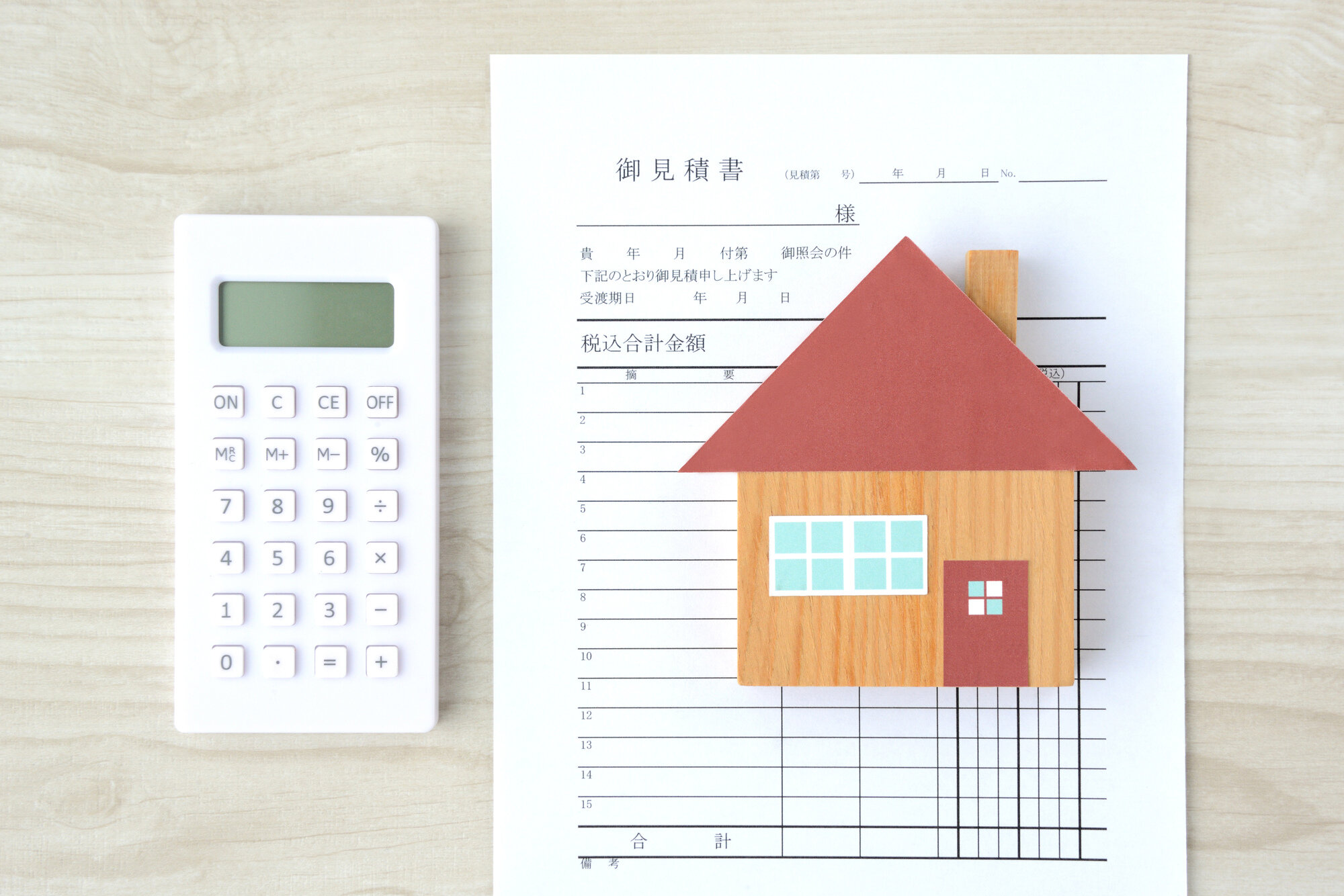
ここまで、法定耐用年数とは税制上の建物の価値を示すためのもので、確定申告時の減価償却費などの計算に用いられることを解説しました。それでは、売却や借り入れの場面では、法定耐用年数はどのような影響を及ぼすのでしょうか。
不動産会社に所有する賃貸住宅の売却を依頼したり、金融機関に修繕費の借り入れを申し込む際には、建物の価値を算出する査定が行われますが、この査定は、築年数から法定耐用年数を引いた「残存耐用年数」が重視されます。一般に残存耐用年数が多いほど(築年数が経過していないほど)売却時の査定額が高くなり、建物の担保価値が高いと見なされることで借り入れ可能額も増えます。
もちろん、査定の際に重視されるのは残存耐用年数だけではなく、
などがあります。
建物の築年数が経過すると、修繕や大規模なリフォームをする必要が出てきます。修繕やリフォームを行った際には、いつどのような修繕をしたかという履歴を残しておくことで査定時に高く評価してもらえる可能性があります。
建物の構造によって異なる法定耐用年数は、確定申告、相続、売却など、さまざまな場面で考慮される重要な数字です。賃貸住宅経営の収支計画にも影響することから、建物の構造について事前にしっかりと検討することが大切です。
 |  |  |